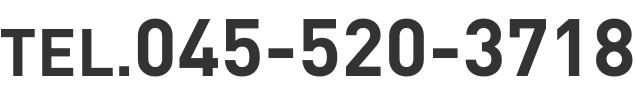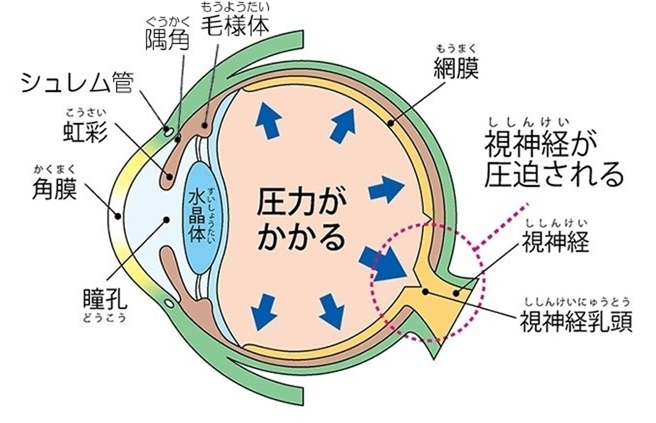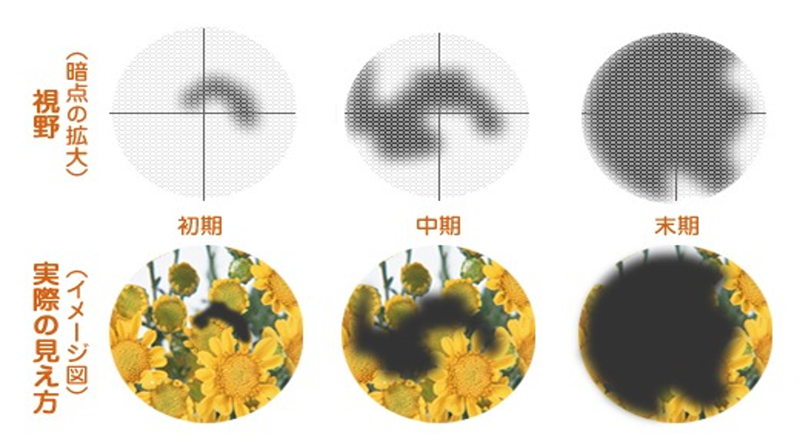白内障
白内障とは
白内障は目の中のレンズの役割を担う水晶体がにごる病気で、早い方は40歳代から発症し、80歳を過ぎるとほとんどの方に白内障の症状が見られるようになります。
ほとんどが加齢による変化ですが、糖尿病やアトピー、外傷などの疾患から白内障になる場合もあります。
指紋で汚れたメガネで見るとぼやけて見えるように、白内障により水晶体が濁ると霞んで見えづらくなります。
<早めの眼科受診をしましょう>
白内障はよく「老眼」と混同されます。
白内障の初期と発症する時期が重なるため、光がまぶしく色の区別がつきにくいといった白内障の代表的な症状を自覚しても老眼の症状として勘違いされる方もいます。
眼の病気は自覚症状が少なく、何らかの異常に気付いた時には早めの眼科受診をお勧めいたします。
白内障は、進行する病気です。
進行すると手術の難易度が高くなる場合もありますので、適切な時期に手術を受けることが重要です。
さらに近年ではパソコンを使った仕事が普及したため30代から発症する「若年型白内障」が増えてきています。
白内障と同時に近視、遠視、乱視、老眼のすべてを治療できる多焦点眼内レンズも登場していますので、当院では早い段階で手術を検討する方も多くなっています。
白内障の症状
白内障は非常にゆっくりと進行するため、ふつう初期の白内障では自覚症状はありません。
進行すると次第に見えにくさを自覚するようになります。
最も多いのは雲がかかったようなかすみで、白黒や色のくっきり度が低下します。
天気がいい日の日差しや、夜間の運転時の対向車のライトがとても眩しく感じるようになります。
近視や乱視の度数が変化して、それまで使っていたメガネが合わなくなります。
近視がとても強く進行するにごり方もあり、このタイプの白内障では同時にものが二重や三重にダブって見える現象が生じます。
白内障の種類
皮質白内障
「皮質白内障」は水晶体のまわりの部分(皮質)から、くさび形の濁りが生じます。
外からの光は水晶体の中央部分を通るため、濁りが瞳の真ん中(瞳孔)まで到達しなければ、まったく症状は起こりません。
白内障で最も自覚症状の出にくいのが「皮質白内障」です。
一方で濁りがいったん瞳孔まで届いてしまうと、そこから先の進行は早くなります。
濁りが瞳の中央にかかると、そこで光が乱反射を起こして症状が出るようになり、さらに進行すると瞳全体が濁ってしまい、視力は急速に低下していきます。
<皮質白内障の特徴>
- 物がダブって見える。
- まぶしく視界全体がかすんで霧がかかったようになる。
核白内障
「核白内障」は水晶体の中央の核の部分からだんだん硬くなり、茶色く濁ってきます。
このタイプは水晶体の中央から均一に濁りが生じるので、医師でも診断がつきにくく見逃されてしまう場合もあります。
白内障の中でも最も診断がつきにくいのが「核白内障」です。
核白内障が進行し、水晶体がガチガチに硬くなってしまうと、手術の際の合併症のひとつである「後嚢破損」が起こるリスクが高まります。
核白内障と診断されましたら早いうちの対処をおすすめします。
<核白内障の特徴>
- 近視が進んだ状態になり、メガネの度数をあげても視力が出づらくなる。
- 紺色が黒に見えたり、白と黄色の区別がつきにくくなったり、色の識別がつきにくくなる。
後嚢下白内障
「後嚢下白内障」は水晶体の光の通り道である中央部にすりガラス状の濁りが生じます。
このタイプは初期のころからまぶしさを感じたり視力低下の症状が現れやすく、急速に進行しやすいのが「後嚢下白内障」です。
原因は加齢だけでなく、リウマチ・膠原病・喘息などで副腎皮質ステロイドホルモンの長期間服用や、糖尿病・アトピーの方などにもよく見られます。
特にアトピー性の白内障は10代から20代で発症することもあります。
<後嚢下白内障の特徴>
- 急激に視力が低下する。
- 光の通り道が濁るため、光が眼球の中で散乱し、まぶしさを感じやすい。
前嚢下白内障
「前嚢下白内障」は水晶体を包む前嚢の真ん中にヒトデ型の濁りが生じます。
パソコンを使う仕事などの影響で、30代から40代の若い人達に増えています。
後嚢下白内障と同様に水晶体の光の通り道である中央部から濁りが生じるため進行も早いです。
パソコンとの因果関係を含め、原因はまだ解明されていません。
<前嚢下白内障の特徴>
- 急激に視力が低下する。
- 濁りが小さいうちは瞳孔が広がる夜間の方が良く見える。
白内障の治療
点眼薬の使用や唾液腺ホルモンなどの内服を行うことがありますが、混濁してしまった水晶体をもとの状態に戻すことはできません。
目薬は白内障の発症を防止または濁りの進行を遅らせることしかできないため、進んでしまった白内障に対する根本的な治療は手術しかありません。